最終更新日:2025年7月4日
千葉県鎌ケ谷市鎌ヶ谷大仏在住の渡辺様(仮名)の解決事例
借入総額
600万円→ 120万円
毎月の返済額
不明→ 3万5000円
ご相談までの背景
渡辺さん(仮名)は、当初は別の弁護士に破産手続きを依頼していましたが、その弁護士の体調不良を理由に突然辞任を告げられてしまいました。
突然の弁護士辞任により、渡辺さんは今後どうすれば良いか分からなくなり、当事務所へ相談に来られました。
弁護士が詳しくお話を伺ったところ、渡辺さんは前の弁護士の指示に従い、弁護士に依頼した後も会社への借入金の返済を半年以上継続していたことが分かりました。
さらに、キャリア決済による新たな借入・返済も続けていたことが判明しました。
これらは破産手続上、大きな問題となる行為です。
渡辺様の状況のまとめ
- 債務総額は600万円超
- 個人事業主(軽配送業)
- 弁護士介入後に借入と返済を繰り返していた
- 突然弁護士から辞任を告げられた
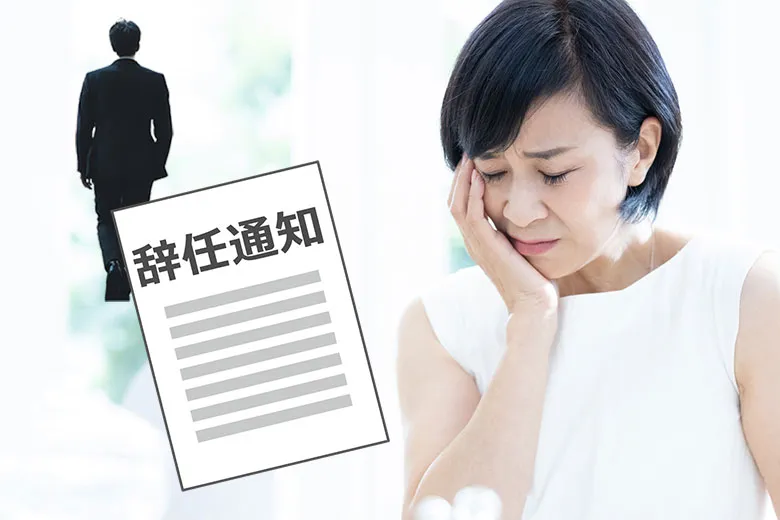
解決までの流れ
1. 借入・返済を継続していた点の解決方法
本件の最大の問題は、以下の2点です。
- ① 弁護士介入後も会社への返済を続けていたこと
- ② 弁護士介入後もキャリア決済による借入・返済を継続していたこと
まず、①会社への返済については、破産手続きにおいて「偏頗(へんぱ)弁済」と見なされ、破産管財人が会社に対して返済金の返還を求める「否認権」を行使する可能性があります。
これにより、渡辺さんは会社に居づらくなり、最悪の場合退職せざるを得なくなる恐れがありました。
会社を退職することになれば、渡辺さんの生活再建に大きな支障をきたすため、この事態は絶対に避けなければなりません。
次に、②キャリア決済による借入も、同様に偏頗弁済の問題が生じます。
加えて、支払い停止後も新たな借入を継続していたとなれば、破産手続きを進めても、継続的な借入が無ければ生活ができないということもあり、裁判所が厳しい判断をする可能性がありました。
2. 破産ではなく、個人再生を選択
個人再生手続では、破産管財人が選任されることはなく、偏頗弁済分は「清算価値」として計算に組み込まれるだけです。
そのため、弁護士介入後に返済を継続していても、それを清算価値に反映させれば個人再生手続きを進めることができます。
これにより、会社への返済が問題になることはなく、会社との関係を維持しながら生活の再建を目指せます。
こうした観点から、渡辺さんの場合、破産よりも個人再生の方が適していると判断し、個人再生手続を選択しました。
3. 個人事業主の履行可能性
個人再生手続においては、将来的に計画通りに返済を続けられるかどうか(履行可能性)が重要です。
個人事業主は会社員に比べ収入が不安定と考えられるため、裁判所は特に慎重に確認します。
しかし、渡辺さんは、軽配送業務において毎日一定の荷物を運ぶという比較的安定した収入が得られる契約内容であったため、その点を詳細に説明しました。
これにより、履行可能性について裁判所の理解を得ることができ、再生委員の選任も不要とされ、無事に開始決定が出されました。
4. 履行テストと再生計画認可決定
個人再生手続きでは、履行可能性の確認のために「履行テスト」を実施します。
これは、実際に毎月想定される弁済額を弁護士の預り金口座へ振り込み、計画通りに返済が可能であることを証明するものです。
渡辺さんは毎月遅れることなく履行テストを実施し、履行可能性に問題がないことを証明しました。
最終的に再生計画案は債権者の決議に付され、一部の不同意意見はあったものの無事に再生計画案が認可され、手続は終了しました。
相談時:600万円→手続き後:120万円
相談時:不明→手続き後:3万5000円
弁護士のコメント
1. 個人再生手続とは
個人再生手続は、原則として3年の期間で、圧縮された債務を計画的に返済していくという債務整理の方法です。
具体的な返済総額は、それぞれの事情によって異なります。ここでは、もっとも利用されることの多い「小規模個人再生」に焦点を当てて解説します。
小規模個人再生手続では、圧縮後の債務額と「清算価値」(簡単にいうと財産の総額)を比較し、そのうち高い方が返済総額となります。
例えば、圧縮後の債務額が100万円で清算価値が50万円の場合、返済総額は100万円になります。
一方で、圧縮後の債務額が100万円、清算価値が200万円の場合には、返済総額は200万円となります。
2. 債務の圧縮の基準
債務の圧縮額は、以下の表のとおり定められています。
| 債務総額 | 圧縮後の額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 圧縮されない |
| 100万円~500万円以下 | 100万円 |
| 500万円~1500万円以下 | 債務総額の2割 |
| 1500万円~3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円以下 | 債務総額の1割 |
例えば、債務総額が300万円の場合は100万円にまで圧縮され、債務総額が1000万円の場合は200万円にまで圧縮されます。
3. 清算価値とは
清算価値とは、非常に簡単に言えば、持っている財産の総額のことを指します。以下の例で考えてみましょう(千葉地裁の基準によります)。
| 預貯金 | 30万円 |
|---|---|
| 自動車 | 50万円 |
| 保険の解約返戻金 | 10万円 |
| 財産の合計 | 90万円 |
| 清算価値 | 90万円 |
この場合、清算価値は90万円と評価されます。
ただし、現金については取扱いが若干異なります。
| 現金 | 110万円 |
|---|---|
| 預貯金 | 30万円 |
| 自動車 | 50万円 |
| 保険の解約返戻金 | 10万円 |
| 財産の合計 | 200万円 |
| 清算価値 | 101万円 |
現金については99万円までなら清算価値に含めないという運用が多いです。
したがって、110万円の現金のうち、99万円を差し引いた11万円だけが清算価値に含まれることになります。
4. 偏波弁済と個人再生手続きの影響
それでは、偏頗弁済があった場合、個人再生手続にはどのような影響があるのでしょうか。
結論としては、偏頗弁済分の額を清算価値に上乗せする必要があります。
例えば、偏頗弁済分が30万円のケースを考えます。
| 現金 | 110万円 |
|---|---|
| 預貯金 | 30万円 |
| 自動車 | 50万円 |
| 保険の解約返戻金 | 10万円 |
| 偏頗弁済額 | 30万円 |
| 財産の合計 | 230万円 |
| 清算価値 | 131万円 |
このように、偏頗弁済分の30万円が上乗せされ、清算価値が131万円になります。
この清算価値を前提にすれば、偏頗弁済があったとしても個人再生手続きを行うことが可能です。

本解決事例についてのご質問と回答
個人事業主でも個人再生手続を利用できますか?
小規模個人再生の要件として、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」が必要とされます。
個人事業主であっても、少なくとも3か月に1度のペースで返済できる程度の収入があれば、この要件を満たし、個人再生手続きを行うことが可能です。
弁済期間を3年以上にすることはできますか?
個人再生における弁済期間は原則3年ですが、「特別の事情」がある場合には5年を限度として延長が認められます。
この「特別の事情」とは、3年での弁済が現実的に困難であることを指します。
例えば、3年間で100万円を返済する場合、月々の返済額は約2万8000円となりますが、もし毎月2万円しか返済に充てられないとすれば、3年では返済が不可能です。この場合、弁済期間を5年に延ばすことにより、月々の返済額を約1万7000円に抑えることができます。
債権者の同意がないと個人再生ができないと聞きましたが、本当ですか?
小規模個人再生手続では、①債権者の人数の過半数が同意すること、②同意した債権者の債権額が総債権額の2分の1以上であることが必要です。
例として、以下のような借入がある場合を考えます。
| A社 | 200万円 |
|---|---|
| B社 | 50万円 |
| C社 | 30万円 |
B社とC社が同意しない場合、頭数として過半数の同意がないため、手続きを進めることができません。
また、仮にB社とC社が同意しても、A社が同意しない場合には、同意した債権者の債権額が総額の2分の1を下回るため、やはり手続きは進められません。
債権者の同意が得られない場合には、債権者の同意を要しない「給与所得者等再生」の利用を検討することになります。
ただし、給与所得者等再生では小規模個人再生に比べ弁済総額が多くなることが一般的です。
また、「給与またはこれに類する定期的な収入が見込まれ、その収入額の変動幅が小さいこと」という厳しい要件が課されるため、利用のハードルは高くなります。
不同意の意見はどれくらいの可能性で出ますか?
多くの債権者は不同意の意見を提出しないため、ほとんどのケースでは問題なく小規模個人再生を利用できます。
ただし、少数ではあるものの、不同意を出す債権者が存在することも事実です。
弁護士は、どの債権者が不同意を出す傾向にあるかを把握しているため、不安がある場合は事前に弁護士へ相談されることをおすすめします。
個人再生委員はどのような場合に選任されますか?
個人再生委員は、個人再生手続きにおいて裁判所が選任する弁護士です。
その職務は①再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること、②再生債権の評価に関し裁判所を補助すること、③再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすることの3点になります。
千葉地方裁判所では、裁判所が必要と認める場合に限り個人再生委員が選任されます。
例えば、履行可能性に疑義がある場合、財産状況を調査する必要がある場合、浪費やギャンブルがある場合などです。
個人再生委員が選任される場合、その個人再生委員への報酬として15万円~20万円が必要となります。
履行テストで積み立てた額から、個人再生委員の報酬に充てられるケースが多いです。
※プライバシー保護のため、お客様住所は実際の住所ではなく近隣の住所を記載していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
(監修者:弁護士 米井舜一郎)







監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 米井舜一郎